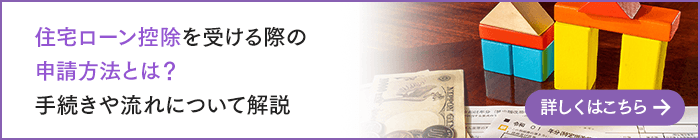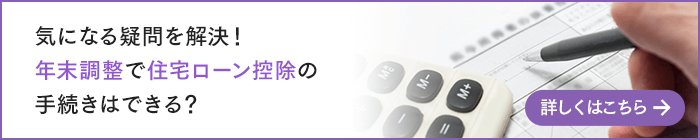住宅ローン控除の期間は?2022年度に改正された情報を徹底解説!我が家は対象になる?

住宅ローン控除は、住宅ローンの借入残高に応じて所得税の控除が受けられる制度です。2022年度に4年間延長された際に、制度内容が大きく改正になりました。
これから住宅を買う予定の方の中には、「自分は新しいタイプの住宅ローン控除を使えるのだろうか」、「最新の住宅ローン控除の制度の内容を知りたい」」というお考えの人が多いと思います。この記事では、2022年度からスタートした新しい住宅ローン控除の内容を解説します。
目次
新しい住宅ローン控除とは?
住宅ローン控除は2022年度から、対象となる住宅、借入金の限度額、税額控除の率、控除期間が大きく変わりました。制度の内容は以下のとおりです。
表1 新築住宅等・買取再販住宅等
| 居住開始の年 | 対象となる住宅 | 控除対象となる 借入金の限度額 |
税額控除の率 | 控除期間 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年 2023年 |
長期優良住宅 低炭素住宅 |
5,000万円 | 0.7% | 13年 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 4,500万円 | |||
| 省エネ基準適合住宅 | 4,000万円 | |||
| その他の住宅 | 3,000万円 | |||
| 2024年 2025年 |
長期優良住宅 低炭素住宅 |
4,500万円 | ||
| ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | |||
| 省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | |||
| その他の住宅*1 | 2,000万円 | 10年 |
- 2023年12月31日までに建築確認済または2024年6月30日までに建築済の住宅に限る
- (出典)下記資料を基に筆者作成
国税庁ウェブサイト No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)
表2 新築住宅等・買取再販住宅等以外(中古住宅等)
| 居住開始の年 | 対象となる住宅 | 控除対象となる 借入金の限度額 |
税額控除の率 | 控除期間 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年〜 2025年 |
長期優良住宅 低炭素住宅 ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅 |
3,000万円 | 0.7% | 10年 |
| その他の住宅 | 2,000万円 |
- (出典)下記資料を基に筆者作成
国税庁ウェブサイト No.1211-3 中古住宅を取得し、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)
対象の住宅について解説
ここでいう「新築住宅等」とは、住宅の新築または建築後使用されていない住宅の取得のことをいいます。また、宅地建物取引業者が一定の増改築等を行い販売する、定められた基準を満たしている既存住宅は「買取再販住宅」として表1に該当します。一方で、個人間取引で中古住宅を購入するケースは表2に当たります。
長期優良住宅は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づいて同住宅として証明された住宅のことをいいます。長期優良住宅として認定されるためには、戸建の場合は劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、省エネ性を満たす必要があり、マンション等の場合は合わせて可変性やバリアフリー性が求められます。また、居住環境、住戸面積、維持保全計画、災害へ配慮もチェック項目になっています。
低炭素住宅は、都市の低炭素化の促進に関する法律に基づいて同住宅として証明された住宅のことをいいます。低炭素住宅として認定されるためには、一定の省エネ基準を満たしていることや、再生可能エネルギー設備の設置などが求められます。
ZEH水準省エネ住宅とは、断熱などの省エネ設備と太陽光発電などの発電設備を併用することで、年間の一次エネルギー消費量の収支をゼロにすることを目指した住宅です。ZEHはネット・ゼロ・エネルギー・ハウスの略称です。
省エネ基準適合住宅とは、長期優良住宅、低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅以外の住宅で、断熱等性能等級及び一次エネルギー消費量等級が4以上の住宅です。
上記に該当しない住宅がその他の住宅に分類されます。なお、住宅ローン控除の対象物件は、居住用部分の面積が2分の1以上、床面積が50㎡以上であることが定められています。ただし、新築等で40㎡以上50㎡未満かつ、2023年12月31日以前に建築確認を受けた新築等の物件は、合計所得金額1,000万円以下の年に限り対象になります。
ちなみに、中古物件で新耐震基準を満たしていない物件は住宅ローン控除の対象外になります。1982年1月1日以降に建築された建物は、新耐震基準を満たしたしているものとみなされます。
控除額について解説
住宅ローン控除は、その年の年末時点の借入残高の0.7%に相当する金額が、所得税から控除される制度で、正式名称は”住宅借入金等特別税額控除”と言います。所得税から控除しても控除額が残る場合は、最大で97,500円まで住民税からも控除できます。
例えば、新築の長期優良住宅を購入し、年末の借入残高が5,000万円ある人の控除額は、上記の表に当てはめて計算すると、下記のようになります。
5,000万円×0.7%=35万円
年末の借入残高が4,000万円の方は、上記計算式の5,000万円部分を4,000万円にして計算します。一方、借入残高が5,000万円以上ある場合でも、5,000万円で計算します。長期優良住宅の控除対象となる借入金の限度額は5,000万円だからです。
毎年、年末の借入残高に対して同じ計算式で控除額を計算し、物件に応じて最大で13年間または10年間の控除を受けることができます。
物件要件以外の住宅ローン控除の適用要件
住宅ローン控除を受けるためには、物件の要件以外にも以下のさまざまな要件を満たす必要があります。
【物件要件以外の住宅ローン控除を受けるための主な要件】
- 住宅購入後6ヶ月以内に住み、住宅ローン控除を受ける年末まで住み続けること
- 合計所得金額が2,000万円以下であること
- 住宅ローンの返済期間が10年以上であること
上記のとおり、住宅ローン控除を受けるためには、居住していることが要件となります。たとえば、別荘や店舗、賃貸用の投資用物件等で借りたローンは、住宅ローン控除の対象外です。
「合計所得金額2,000万円以下」という要件の合計所得金額とは、「給与所得、事業所得、不動産所得、雑所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得の損益通算後の合計額」及び「総合課税の長期譲渡所得と一時所得の損益通算後の合計額の2分の1の額」及び「退職所得及び山林所得」の合計額のことです。会社員で給与所得のみ方は、給与収入から給与所得控除を引いた金額が合計所得金額になります。
「返済期間10年以上」の要件は、多くの方が問題なく満たせるのではないでしょうか。ただ、繰上げ返済をすることで返済期間が10年未満となった場合は、住宅ローン控除の対象外になってしまう点には注意が必要です。
住宅ローン控除の対象とならない場合とは?
ここから、住宅ローン控除の対象にならない場合について解説します。
贈与による取得、および取得の時、取得後も引き続き生計を一にする親族、特別な関係のある人からの取得の場合
贈与で取得した住宅や生計を一とする親族などからの取得の場合は、住宅ローン控除利用ができません。
居住の用に供する住宅を2つ以上所有する場合
自宅を2つ以上所有する場合は、主に居住している1つの住宅分の借入金のみ住宅ローン控除の対象となります。
親族や知人からの借入金で住宅を取得した場合
住宅ローン控除の対象となるのは、金融機関や指定基金、住宅資金の貸金業者から借り入れた場合に限られています。
土地のみ購入の際の借入金
住宅用の土地であっても、土地のみの購入の場合は、住宅ローン控除の利用ができません。土地のみ借入金で購入、建物部分は自己資金や親族からの借り入れで取得する場合も、住宅ローン控除の対象外となります。
ちなみに、先に土地を購入する場合は、2年以内に住宅を建てるのであれば、住宅ローン控除の対象となります。例えば、「5年後に家を建てるための土地の購入」であれば、土地部分購入のための借入金は住宅ローン控除対象にはなりません。
また、建築条件付き土地の場合は、3ヵ月以内に建物の契約を締結することが必要です。あわせて、土地のみ借入金で購入、建物部分は自己資金や親族からの借り入れで取得する場合は、住宅ローン控除の対象外となります。
住宅ローン減税についてはこちらの記事もご覧ください。
住宅ローン控除と併用できない譲渡所得の課税の特例を受けている
住宅ローン控除と併用できない譲渡所得の課税の特例は以下のとおりです。これらの制度を居住の年とその前後2年の間(2020年4月1日以後の譲渡の場合は、居住の年とその前2年、その後3年の合計6年間)に利用している方は、住宅ローン控除を受けられません。
- 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
- 居住用財産の譲渡所得の特別控除(被相続人の居住用財産の譲渡所得の特別控除による場合を除く)
- 特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例
- 財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例
- 既存市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例
住宅ローン控除を受ける際の手続きについて
確定申告を行った場合に住宅ローン控除を受けることができます。給与所得者の場合は、取得した住宅に居住開始した年(住宅ローンの支払いを開始した年)の翌年だけは確定申告が必要です。一方で、自営業の人は毎年の確定申告と一緒に手続きを行います。
確定申告についての詳細は以下の通りです。
- 期間:毎年2月16日~3月15日
- 土曜日・日曜日・祝日・休日の場合は翌営業日が期限日。
確定申告時に主に必要な書類と取得できる場所も確認しておきましょう。
| 書類 | 取得できるところ |
|---|---|
| 確定申告書(A)*2 | 税務署や国税庁サイト |
| 住宅借入金等特別控除額の計算明細書 | 税務署や国税庁サイト |
| 住宅ローン残高証明書 | 住宅ローン契約中の金融機関から送付 |
| 登記事項証明書 | 法務局 |
| 新築の工事の請負契約書の写し | 建築会社・不動産会社 |
| 売買契約書の写し | 不動産会社 (土地・建物の取得時に不動産会社と取り交わしたもの) |
| 源泉徴収票 | 勤務先 |
| 本人確認書類*3 | 市区町村役場 |
| 長期優良住宅 低炭素住宅 ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅の場合 認定通知書や証明書 |
自治体、建築士等 |
- 会社員など通常確定申告をしない人の場合
- 以下の中から選択して写しを提出
1.マイナンバーカード
2.マイナンバーカード
(もしくはマイナンバーが記載されている住民票)
+運転免許証などの本人確認書類
住宅ローン2~10年目(延長期間中の住宅取得・居住開始であれば13年目まで)は、勤務先の年末調整時に書類を提出するだけで、住宅ローン控除手続きは終了します。年末調整で必要な書類は、次の通りです。
- 「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」兼「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」
- 「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」
「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」兼「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」は住宅ローン控除のための確定申告をした後に、税務署から送られてきます。2~10年目分(もしくは13年目分)は、まとめて送られてきますので、控除年数が終了するまで大切に保管しておきましょう。
紛失した場合は、申請書(国税庁HPからダウンロード可能)を税務署に持参、もしくは送付し、再発行手続きを行わなければなりません。
「年末残高等証明書」は、住宅ローン契約をしている金融機関から毎年10月ごろに送付されてきます。住宅ローン契約をする金融機関を考える際は、控除の申請をする際に慌てないように住宅ローン控除の手続きについても確認しておくようにしましょう。
なお、2023年1月1日に住み始める住宅については、住宅ローンを借りる金融機関に氏名、住所、個人番号などが記載された「住宅ローン控除申請書」を提出する必要があります。この申請書を提出することで、確定申告時に「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」や「新築の工事の請負契約書の写し」等の添付が不要になります。年末調整時も「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の提出が不要になります。ただし、税務署が急遽これらの書類の提出を求める場合があるので、保管はしておきましょう。
住宅ローンの借り換えをした場合、控除はどうなる?
住宅ローンは、最長35年という長期間の契約になることが予想されるローンです。もし、返済中に他の住宅ローンに借り換えをしたら、住宅ローン控除はどうなるのでしょうか。原則、住宅ローン控除の対象は、住宅の取得・増改築のために必要な借入金です。
通常であれば、借り換えは今までの住宅ローンを返済するための資金で、住宅の取得とは直接関係がない資金とみなされるため、住宅ローン控除の対象とはならないと感じる人もいるかもしれません。しかし、以下を満たせば、借り換えであっても住宅ローン控除対象の住宅ローンとされるため、確認しておきましょう。
- 新しい住宅ローンが当初の住宅ローン返済のためのものと明確であること
- 新しい住宅ローンが10年以上の借入期間など、住宅ローン控除の対象条件に当てはまること
住宅ローン控除が受けられるのは「居住の用に供した年から一定期間(10年、もしくは13年)です。そのため、借り換えをしても控除期間が延びるわけではありません。借り換えで借入期間を10年未満に変更した場合は、住宅ローン控除自体、対象外となるため注意が必要です。
住宅ローン控除期間の延長条件をよく確認しておこう!
住宅ローン控除は過去から現在にかけて何度も改正されてきました。特に2022年度の改正は、かなり大幅なものになりました。住宅の性能によって最大の控除額は細かく分かれており、制度の内容を見る限り、環境に配慮した住宅の普及への後押しになっていると感じられます。今後も、住宅ローン控除は改正を繰り返していくものだと推測できます。最新の制度の内容について詳しくは国税庁のホームページ等でご確認ください。
SBI新生銀行では便利なシミュレーションツールをご用意しております。
住宅ローンシミュレーションはこちら- 本稿の内容は2021年10月に作成し2022年11月に更新したものです。

えんどう こうじ
- CFPR
- 1級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
株式、債券、金利、為替、REIT等、マーケットの変動がその価格等に影響を及ぼす金融商品を購入する際は、必ず個別金融商品の商品説明書等をご覧・ご確認いただき、マーケットの動向以外に、各金融商品にかかる元本割れなどの固有のリスクや各種手数料についても十分ご確認いただいた上でご判断ください。
本稿は、執筆者が制作したもので、SBI新生銀行が特定の金融商品の売買を勧誘・推奨するものではありません。
- 本資料は情報提供を目的としたものであり、SBI新生銀行の投資方針や相場観等を示唆するものではありません。
- 金融商品取引を検討される場合には、別途当該金融商品の資料を良くお読みいただき、充分にご理解されたうえで、お客さまご自身の責任と判断でなさるようお願いいたします。
- 上記資料は執筆者が各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性をSBI新生銀行が保証するものではありません。
当行では具体的な税額の計算、および、税務申告書類作成にかかる相談業務はおこなっておりません。個別の取り扱いについては、税理士等の専門家、または所轄の税務署にご確認ください。
新着記事
閲覧が多い記事
おすすめ記事
マイページへ登録済みの方は
住宅ローンマイページお問い合わせ
ビデオ通話などでの相談をご希望なら
住宅ローン相談住宅ローン
パワースマート住宅ローンについて
- 借入期間は5年以上35年以内(1年単位)、借入金額は500万円以上3億円以下(10万円単位)です。
- 変動金利(半年型)、当初固定金利をご選択された方は、当初借入金利適用期間終了後、ご契約時の事務手数料に応じた変動金利(半年型)が自動適用となります。
- 変動金利(半年型)、当初固定金利を利用されている方は、金利変更時に当初固定金利タイプをご選択いただくことも可能です。ご選択にあたっては、手数料5,500円(消費税込み)がかかります。
- 各金利タイプは、金利情勢等により、やむを得ずお取り扱いを中止する場合もございます。
- SBI新生銀行ウェブサイトにて、借入金額や借入期間に応じた毎月の返済額を試算できます。
- 事務手数料は、定額型をご選択された場合55,000円(消費税込み)、定率型をご選択された場合、借入金額に対して2.2%(消費税込み)を乗じた金額となります。それ以外に抵当権設定登録免許税、印紙税*、司法書士報酬、火災保険料等がかかります。*電子契約サービスをご利用の場合、印紙税は不要ですが、別途電子契約利用手数料5,500円(消費税込み)がかかります。
- ご融資の対象物件となる土地、建物に、当行を第一順位の抵当権者とする抵当権を設定いただきます。
- パワーコール<住宅ローン専用>、SBI新生銀行ウェブサイトにて商品説明書をご用意しています。
- 当行の住宅ローンを既にご利用中のお客さまにつきましては、当行で借り換えをすることができません。
- 住宅ローンのご融資には当行所定の審査がございます。審査結果によっては、表示金利に年0.10%~年0.15%上乗せになる場合がございます。ご希望にそえない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
[2024年1月22日現在]